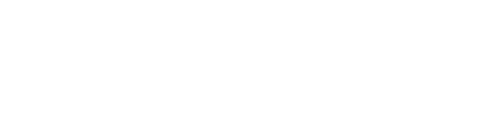法22条区域とは?住宅購入前に知っておこう!23条も?デメリットも解説
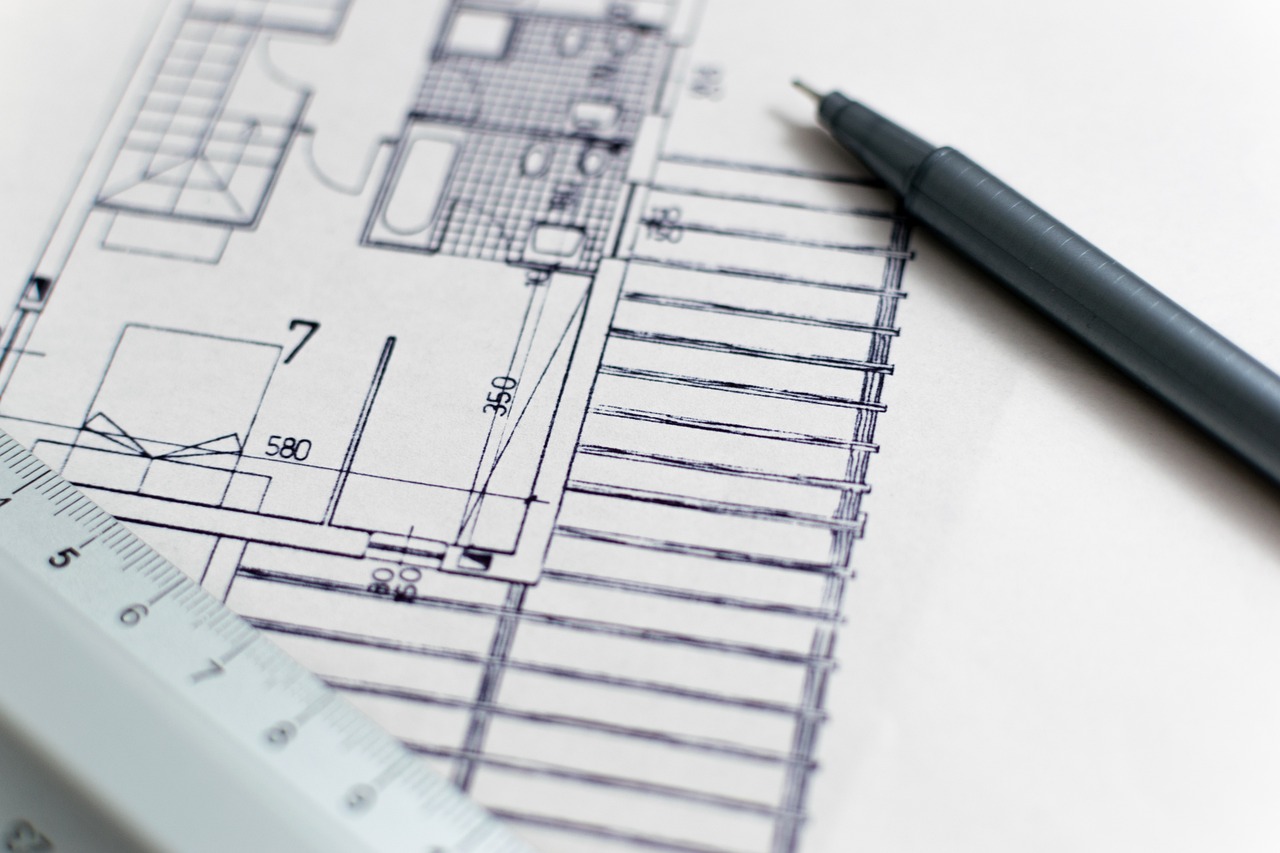
条件もピッタリの住宅を見つけた!けれど、物件情報をよくよく見てみると「法22条区域」…?
何か規制がかかるの?将来困ることはある?1つ1つ疑問を解消してから住宅購入することをおすすめします。
そもそも「法22条区域」とは?
正式名称は「建築基準法第22条指定区域」です。
都市計画の中で、火災の被害が起きやすいエリアは「防火地域」「準防火地域」として定められます。そこからさらに一歩外側のエリアを対象に、屋根材などに一定の制限をかけるのが「法22条区域」です。
イメージとしては、防火地域 → 準防火地域 → 法22条区域と外側に行くにつれて規制が少しずつ緩やかになる、という感じです。
【22条引用】特定行政庁が、防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために、屋根に必要とされる性能に関して、建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物または延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
木造の建物は更に23条が適用されます。
【23条引用】(法22条区域)の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第61条において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
区域内だと何が起きる?
「屋根」を燃えにくい素材で作らなければいけないという条件がつきます。木造の場合は外壁と軒裏も燃えにくい素材にする必要があります。
- 屋根は燃えにくい素材(不燃材)で作る必要がある
例:コンクリート・瓦・れんが・鉄鋼・ガラス・しっくい など - 木造の場合(23条)
- 外壁や軒裏も燃えにくい素材を使用
- 隣地境界線から1m以内は「防火構造」にする必要あり
- 軒裏は不燃材または準不燃材で仕上げる必要あり
注文住宅の場合は、区域内の土地だと使用できる素材に制限がかかることがありますが、建売住宅はすでに基準を満たして建てられているため、購入時に特別な制限を受けることはありません。
デメリットはある?どうカバーする?
- 火災保険料が高くなる場合がある
→ 耐火建築物には様々な割引が用意されてます。住宅性能評価センター等で耐火等級・劣化対策等級を取得すればコストを抑えられる可能性があります。 - 資産価値が落ちやすい傾向
→ 防火サッシや防火戸の点検記録などをきちんと保管しておけば査定時にプラス材料になります。性能評価書も保管し、提出しましょう。 - リフォーム費用が高め
→ 屋根材や防火部材にコストがかかるため、積立や相見積もりで対策をしましょう。
リフォーム時の注意点
防火地域や準防火地域だと、わずかな増築でも建築確認が必要ですが、法22条区域では10㎡以下なら確認不要です。
制限は基本的に「屋根(木造は外壁や軒下も)」に限られるため、デザインの幅は狭まりにくいです。
まとめ
法22条区域は、建物が比較的密集する利便性の高いエリアに指定されることが多く、生活面ではメリットも大きいです。
制限があると聞くと不安に感じるかもしれませんが、実際には「火災に強い家を持てる」という安心感につながります。
法22条区域=安心して暮らせる街づくりのためのルール。そう捉えれば、むしろ住みやすさの裏付けになるかもしれませんね。